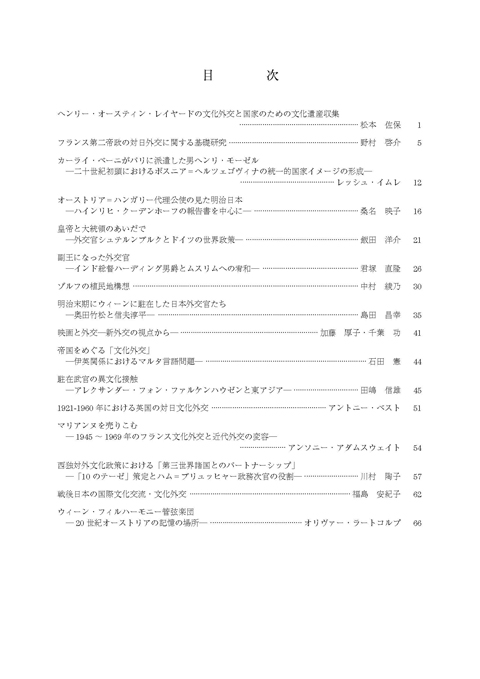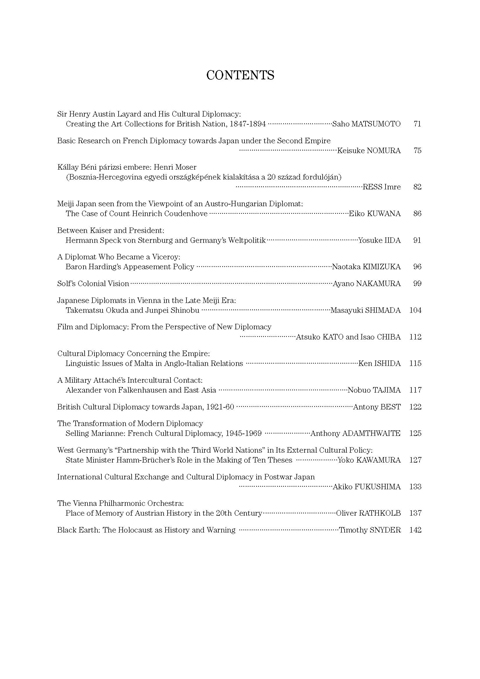「異文化交流と外交」研究会
JSPS 科学研究費補助金 基盤研究(B)

旧ハプスブルク帝国外務省(ウィーン、バルハウス広場)
研究報告要旨
ディルクセンとトラウトマン/成城大学・田嶋信雄

ドイツ外務省政治文書館
ヘルベルト・フォン・ディルクセン(Herbert von Dirksen, 1882-1955)とオスカー・トラウトマン(Oskar Trautmann, 1877-1950)は1930年代ナチス・ドイツの東アジア政策における重要なアクター(それぞれ駐華大使および駐日大使)であると同時に、ドイツ東アジア政策に関する外交目標の設定および実践において著しい対照性を示したことでも知られる。すなわちディルクセンは1935年9月にベルリンで始まる日独防共協定交渉を東京から側面的に支援し、ナチズム東アジア政策における親日政策の形成に寄与したが、他方トラウトマンは中国にあってドイツ対中政策と対日政策のバランスに配慮するとともに、ナチス・ドイツ政府、とりわけ国防省や経済省の中国に対する過度の政治的・経済的コミットメントにも警告を発し続けた。これをナチ・イデオロギーの外交的側面に即していえば、ディルクセンはナチズム親日政策に親和的であり、トラウトマンはそれに批判的な態度を示したといえよう。このような二人の差異は、ディルクセンの駐英大使への「栄転」(1938年2月)と、他方でトラウトマンの本国召喚(1938年6月)とその後の外務省における冷遇という運命の差に帰結した。
このような二人の差異はどこに由来するのであろうか。もちろん第一義的には、ナチズム体制前期に二人が派遣された国(日本と中国)の差が大きいであろう。外交官はしばしば自己の駐在国と本国との友好関係の維持・発展に大きな政治的意味を見いだす傾向にある(モートン・ハルペリンのいう「現場の行動様式」)からである。しかしながら、トラウトマンの行動は決して親中一辺倒とはいえず、「現場の行動様式」論からは説明できない面も多い。
そこで本研究計画では、ディルクセンとトラウトマンの依って立つ文化的背景の差異に注目することでこの問題にアプローチすることにしたい。二人の出身階級の差異(貴族的背景をもつディルクセンと教養市民層的背景をもつトラウトマン)、二人の異文化体験の差異(東ヨーロッパ経験の長いディルクセンと東アジア経験の長いトラウトマン)、戦争体験の差異、東アジア文化への関心度・理解度の差異などから二人の政策的態度の差異を対比的に説明することが課題となる。
史料としては、ドイツ連邦共和国外務省外交史料館(ベルリン)および連邦文書館(ベルリン・リヒターフェルデ)に所蔵されているディルクセン関係文書(それぞれ横幅10センチおよび750センチ)およびトラウトマン文書(それぞれ8センチおよび110センチ)が主要な分析の対象となる。
参考文献
Mund, Gerald, Ostasien im Spiegel der deutschen Diplomatie. Die privatdienstliche Korrespondenz des Diplomaten Herbert von Dirksen von 1933 bis 1938, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006.
田嶋信雄『ナチズム外交と「満洲国」』千倉書房 1992年。
――『ナチズム極東戦略』講談社 1997年。
――『ナチス・ドイツと中国国民政府 一九三三-一九三七』東京大学出版会 2013年。
人種主義をめぐる外交問題/千葉大学・石田憲
1.旧外交と新外交における人種主義
- 人権概念の拡大による人種主義の隆盛:同じ人間でありながら何故選挙権を与えないのか
- 「対等な国家関係」をめぐる正当性:非ヨーロッパ圏に対するアプリオリの優越性再構成
- 新外交の中では人種概念は、より明快に展開される必要
- ファシスト・イタリアの下からの運動としての性格:世論動向に対する一般的関心とイタリア駐英大使ディーノ・グランディの役割
2.エチオピア戦争の意味
初めての連盟加盟国に対する全面的な戦争の展開(欧米圏による非欧米圏への侵略)
- アフリカ分割で残された独立国エチオピアに対する先発・後発帝国主義国間の露骨な勢力圏交渉が行なわれた最後の舞台
- 普遍的集団安全保障を担う国際連盟が、結果として被侵略国と中小国に犠牲を強いる、侵略に対する世界初の経済制裁を実施したテスト・ケース
- 社会的ダーウィニズムに基づく戦争賛美を続けてきたファシスト・イタリアが、ようやく手にした武闘の機会
3.戦争正当化をめぐる人種主義の議論
- 「国内的統一」:国内における少数者を攻撃することによる包摂の推進
- 「文明の使節」:ナチ・ドイツの人種主義(反ユダヤ主義)との差異化
- 「劣った存在」:苛烈な軍事行動の正当化
調査予定史料・所蔵館
The National Archives, Kew
Archivio Centrale dello Stato
Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri
副王になった外交官-インド総督ハーディング男爵とムスリムへの宥和-/関東学院大学・君塚直隆
1910~16年のあいだにインド総督を務めたハーディング(Charles Hardinge, 1st Baron Hardinge of Penshurst, 1858~1944)は、1880年に外務省に入省して以来、それまでの30年間にわたって外務事務次官やロシア大使などを務めた外務官僚にして外交官だった人物である。特に、国王エドワード7世(Edward VII、在位1901~1910年)に気に入られ、その片腕として彼が外遊する際には必ず随行し、ヨーロッパ国際政治の表舞台で活躍してきた「旧外交(Old Diplomacy)」の担い手でもあった。
そのハーディングが、エドワード国王の死の直後から、インド総督(副王)として「帝国の中の帝国」と言われ、大英帝国にとって最も重要な植民地の最高責任者に収まった。着任後早々に、イギリス国王自らが臨席しての史上最初にして最後の「インド皇帝戴冠式」(1911年12月)も無事に終えたが、彼の総督在任中にはすでに独立運動の気運も高まり、ベンガル分割(1905年)によるヒンドゥーとイスラームとの衝突も絶えず、ハーディングがそれまで慣れ親しんできた、ヨーロッパ国際政治における外交手法や儀礼だけでは通用しない諸々の問題に直面していくことになる。
本研究では、これまであまり本格的に研究されてこなかった、「外交官」ハーディングのインド総督時代に注目し、特にバルカン戦争(1912~13年)や第一次世界大戦(1914~1918年)というヨーロッパ情勢に対処するにあたって、世界最大のムスリム人口(8000万人)を抱えるインドのイスラーム勢力に気を遣いながら、インド統治と本国への大戦時協力に尽力していた様子を考察していく。
【一次史料】
Hardinge Papers, Cambridge University Library.
Edward VII Papers, The Royal Archives, Windsor Castle.
George V Papers, The Royal Archives, Windsor Castle.
Crew Papers, The National Archives, Kew Gardens, London.
Grey Papers, The National Archives, Kew Gardens, London.
【参考文献】
Lord Hardinge of Penshurst, Old Diplomacy : The Reminiscence of Lord Hardinge of Penshurst(John Murrary, 1947).
Lord Hardinge of Penshurst, My Indian Years, 1910-1916(John Murrary, 1948).
君塚直隆『ジョージ五世-大衆民主政治時代の君主』(日本経済新聞出版社、2011年)。
君塚直隆『ベル・エポックの国際政治-エドワード七世と古典外交の時代』(中央公論新社、2012年)。
ヴィルヘルム期ドイツ外交の一側面―外交官シュペック・フォン・シュテルンブルクの活動から見る異文化交流―/岡山大学・飯田洋介
シュペック・フォン・シュテルンブルク(Hermann Freiherr von Speck von Sternburg, 1852-1908)は帝政期ドイツの外交官の経歴としては極めて異彩を放つ存在である。ザクセン武官の出身であった彼は、ドイツ外務省にあって不遇の身であり、赴任地のほとんどがヨーロッパ圏外ということで、当時の外交官の主流なコースから外れた存在であった。だが、彼は任地の北京やワシントンD.C.での活動が評価されてキャリアアップに成功し、最終的には異例にも駐米大使にまで昇格する。
彼が異彩を放つのはこうしたキャリアだけではない。「旧外交」の時代にあって彼は、「ソフト」面での外交活動にも取り組み、現地社会に積極的に溶け込み、任地の世論にも盛んに働きかけた人物でもあった。貴族社会の風習が支配的であった当時のドイツ外交官の世界では、これは極めて珍しい部類に入る。
彼の東アジアならびにアメリカでの「異文化経験」は、ヴィルヘルム期ドイツの外交政策に果たしてどのような影響を与えたのか。本研究では、シュペック・フォン・シュテルンブルクの北京ならびにワシントンD.Cでの活動の分析を通じて、ビスマルク退陣後のドイツ外交の変容を視野に入れながら、上記の問題を解明していきたい。
【未公刊史料(調査予定)】
- Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin
― Nachlaß Speck von Sternburg
― Personalakten betr. Hermann Freiherrn Speck von Sternburg - Library of Congress, Washington D.C.
― The Papers of Theodore Roosevelt
【参考文献】
Rinke, Stefan H., Zwischen Weltpolitik und Monroe Doktrin. Botschafter Speck von Sternburg und diedeutsch-amerikanischen Beziehungen, 1898-1908, Stuttgart: Han-Dieter Heinz 1992.
飯田洋介「19世紀プロイセン・ドイツの外交官」森原隆編『ヨーロッパ・エリート支配と政治文化』成文堂 2010, 115-131頁.
戦後日本の国際文化交流・文化外交/青山学院大学・福島安紀子
対外国際関係を紡ぐにあたり、文化は冷戦後まで中心的な役割を担わず、周縁的な位置にとどまっていた。冷戦後のグローバル化の進展や、情報通信技術の進歩に伴うIT人口の爆発的な増加により、ソフトパワーの重要性が認識されてきたこともあって、国際関係における文化の役割が注目を集めるようになった。特に近年では広報文化外交(パブリック・ディプロマシー)への関心が高まり、各国が積極的にこの種の外交を展開し、時には競争の様相さえ呈している。しかしながら、日本の歴史をさかのぼると、文化は冷戦の終焉を待つまでもなく、明治維新前後から歴史の様々な局面で重要な役割を果たしてきたことがわかる。
戦後日本においても、終戦直後から外交政策を策定するにあたり、しばしば文化の要素が取り入れられてきた。とりわけ外交上の危機に瀕した時期には、欧米諸国の政策にも触発されながら、外交政策の中に文化交流や文化協力のプログラムが組み込まれてきている。そのような例としては、敗戦直後の日本のイメージ転換、安保闘争、ニクソンショック、貿易摩擦、日本異質論、日本脅威論、米国同時多発テロ、東日本大震災等があげられる。しかし戦後日本では文化と外交を直裁に結ぶことはせずに、あくまでも「国際文化交流」として実践してきた。それは日本が戦前の歴史を念頭に置き、「押し付けにならない」日本文化の紹介や人的交流に力を注いできたことを示している。今後さらに研究を進め、諸外国の政策と比較しながら、日本の「国際文化交流」政策がどのようにして現在のようなパブリック・ディプロマシーへと転換してきたのかを検証していきたい。
マリアンヌを売りこむ—1945〜1969年のフランス文化外交と近代外交の変容/カリフォルニア大学バークレイ・アンソニー・アダムスウェイト
20世紀初頭に文化外交の先駆者となったフランスの体験は、従来型モデルの特長と限界を明らかにし、公共外交への変容を理解する一助となる。本論は1945年から1975年の期間を扱い、第四共和国期(1946〜1958年)とド・ゴールの第五共和国期(1958〜1969年)を含む。この時期はフランスのグローバルな文化的存在感の黄金時代であった。1945年当時のフランスは、疲弊し破産状態にあった。1940年から1944年におよぶ戦闘や連合軍の空爆により広範な被害を受けてもいた。にもかかわらず、1960年代半ばにはフランスは西ヨーロッパ大陸のリーダーと認められる存在になっていたのである。ドイツの「経済の奇跡(wirtschaftswunder)」に匹敵する奇跡といえるこの驚異的な転回に重要な役割を果たしたのが、文化外交、すなわちソフトパワーである。自分たちには普遍性をもった独自の見解があると再度主張したことで、フランスは二つの点で強化された。国内の自信を強めたこと、そしてフランスには特別な扱いを受ける価値があるとアメリカを納得させたことである。
第四共和国
文化外交は刷新・拡大に注力した。戦時中に閉鎖された多くのアンスティチュやアリアンス・フランセーズ(Alliances francaises)が再開され、英国オックスフォードのメゾン・フランセーズ(1946年)など、新しい研究所も設立された。
刷新・拡大の三段階:
- フランス語指導:学校・研究所のための教員訓練が優先事項となる
- 人文社会科学分野での国際交流の復活
- ハイカルチャーの推進:本の展示会、作家の講演ツアー、映画祭、演劇の巡業(コメディ・フランセーズ)
重要な革新:最重要なのは、外務省(ケ・ドルセー)内部におけるコーディネート機関 Direction generale des relations culturelles et des oeuvres a l’etrangerの創設、主要な大使館への文化アドバイザーの配置、二国間交流/合意、そして文化外交の再定義によりその範囲が文学や芸術のみならず科学技術にも広がったことである。
フランスの文化外交は数多くの利点の恩恵に浴した。フランスには独自の文化的性格があるという意識が1939年〜1945年の戦争と占領期を経ても残っていたこと。フランス的価値観が普遍的価値観と同一視され、人類の進歩を導く灯台としての自己イメージがあったこと。20世紀初頭の文化外交におけるリーダーシップの遺産。
第二次世界大戦の勝者たちはフランスを列強の一員として遇した。フランスには国連の安全保障理事会常任理事国の地位が与えられ、国連、UNESCO、NATOの本部もパリに置かれた(1946年〜1951年)。
1948年、世界人権宣言がパリで採択された。
最重要なのは、1945年から1975年の30年がフランスの知的生活において並外れた創造性が発揮された時期だったことだ。フーコー、デリダをはじめとする多くの思想家は、文化の他の分野(特に歴史学・批評理論、人文科学全般)にも強い影響を与えた。
フランスの売り込みを活気づかせた社会的特徴は他にも二つある。まず、政府・文化・外交の共生関係。フランス国内および海外のハイカルチャーを支えるため、かなりの額の政府予算が投入された。1960年代には、外務省の予算の半分が文化外交に使われていた。政治的・官僚的・文化的エリートがここまで密接に一体化していたのは、おそらくフランスに独特の状況であろう。著名な作家・思想家が公職を目指すこともあった。たとえば詩人で劇作家のポール・クローデルは1920年代に大使として東京に駐在した。
第四共和国の外交はどこまで成功したか?
資金面での欠乏により、第四共和国の文化外交の効果は非常に限定的なものとなった。語学教員の養成や海外への講演ツアーの回数は資金不足のために制限を受けた。1946年にアルベール・カミュが政府の後援を受けアメリカの大学を回って講演をした際には、ぎゅう詰めの貨物船に乗り、5人と共用の船室での旅を余儀なくされた。
第四共和国を「ヨーロッパの病んだ女」とみる国際的なイメージが、フランス的価値観のマーケティングの妨げとなった。政府が毎月替わるような状態では、フランス的価値観の優越性を説得力をもって論じるのは困難だった。
資金難が明らかにしたのは、フランス語の宣伝と文化の伝達の間の緊張関係であった。予算不足のため、フランス語教師の養成に全予算を投入しようとする役人もいた。
世界中でフランス語は守勢に回っていた。1945年にサンフランシスコで開かれた国際連合の設立のための会議では、英語を唯一の使用言語とする提案を退けるにあたり、フランスはソビエト連邦とカナダの力を借りねばならなかった。
第五共和国
威信にこだわるド・ゴール将軍のもと、共和国の文化外交の成功は保証されていた。
- 文化・技術プログラムの拡大の継続。59のアンスティチュ、150の文化センター。180校近いフランス人学校。84ヶ国に800を超えるアリアンス・フランセーズ協会。
- 革新点には以下が含まれる。フランスの初代文化大臣アンドレ・マルロー。新しいグローバルな言語・文化基地であるフランコフォニー国際機関(1970)の発展。1960年代には欧州共同体のリーダーシップにより、フランスが純粋にフランス的というよりはヨーロッパ的価値観を代表する存在であるという主張が新たに強調された。フランス人は自らをヨーロッパ人の典型として描きだした。
結論
1. 文化外交と経済的・軍事的・政治的資源との相互依存
第四共和国は資金難のため、大戦後すぐの時期にはほとんど活躍できなかった。
アルジェリア戦争および冷戦の例
アルジェリアにおけるフランスの拷問や残虐行為は、フランス的価値観が普遍的・進歩的であるという主張と矛盾した。
冷戦にはヨーロッパの意見は含まれていなかった。第二次大戦直後には、フランスの指導者たちは自国が世界政治において第三極となるだろうと考えていた。だが実際には、ソビエト連邦とアメリカ合衆国はハイポリティクスをヨーロッパから切り離してしまった。モスクワとワシントンの両政府が冷戦を管理し、第三の声の入る隙はなかった。フランスや英国といった中堅国は、説得力のある独自の公約を作るのに苦労していた。
2. 英語の容赦ない進攻により、外交語として、また教養あるエリートの共通語としてのフランス語の優位が脅かされた。
18世紀以来フランス語は「法と外交の世界言語」とされてきたが、英語の普及によりフランス語関連の仕事は大幅に縮小し、フランスのハイカルチャーの普及を危うくした。
3. 脱植民地化、グローバル化、および1960年代の文化革命が一体となり、フランスの文化的普遍性という主張に実体がないことを明らかにした。
アルジェリアやインドシナ半島における野蛮な植民地戦争(アルジェリアでは拷問が使用された)は、フランスがリベラルな価値観と人権の守護者であるという言説の偽善を暴いた。
4. 国内では二つの出来事が標準的な文化外交モデルを転覆させた。
1970年代にはフランス国内で文化戦争が勃発し、知識階級は政府による普遍主義的主張に異議を唱えた。また、ムスリム移民によって国民像に変化が生じ、同時に地域に根ざしたアイデンティティやブルトン語のような地域言語の復興が起こったことで、フランス人としてのアイデンティティとは何かという議論に火がついた。ピエール・ノラの『記憶の場(Les Lieux de memoire)』(1984-1992年)は、当時の学術的な議論を反映している。最後に、高度に中央集権的で均質化された国の文化は、多元論的で多文化主義的な世界と折り合いをつけねばならなくなった。
5. 1960年代には西洋型デモクラシー・国家・政治的リーダーシップに対する市民の不信感が加速した。
冷戦期のプロパガンダにより、政治的な虚言が増加した(1956年、スエズ動乱における英仏イスラエルの談合を英国の大臣たちが議会で公式に否定。アメリカ合衆国では、1961年のピッグス湾事件や1964年のトンキン湾事件)。国の政策や発言により、一般に幻滅感とシニシズムが広がった。民主主義や平等主義を志向する市民は、国の価値観や文化のエリート主義的な投影に疑念を抱いた。
6. 1970年以降、文化外交は新しい「パブリック・ディプロマシー」の概念に次第に吸収されていった。
フランス的価値観を他の何よりも優れたものとして一方的に売りつけるという20世紀初頭のシステムに代わって、パブリック・ディプロマシーが強調したのは多文化的な世界における双方向的な協力と参加であった。
第65回日本西洋史学会大会 小シンポジウム2「異文化交流と近代外交の変容」報告要旨
5月17日、第65回日本西洋史学会大会(2日目)が富山大学五福キャンパスにて開催され、 本科研では小シンポジウム2「異文化交流と近代外交の変容」で4名のメンバーが研究発表を行った。
報告要旨は以下の通りである。
趣旨説明 桑名映子
自国の文化を外に向けて発信することにより、国際世論に働きかけようとする外交戦略は、今日「広報文化外交」(パブリック・ディプロマシー)あるいは「対外文化政策」(クルトウーア・ポリティーク)などと呼ばれ、欧米のみならず日本や中国を含むアジア諸国においても、対外政策の重要な柱となりつつある。
歴史的にみても、文化は国際関係において重要な役割を果たしてきた。ウィーン会議後の「旧外交」全盛期には、フランス語を軸としたヨーロッパ教養層の言語的・文化的均質性が、一時的にせよ会議体制を通じた「バランス・オブ・パワー」の達成を可能にした。その一方で、ヨーロッパ諸国からアジアやアフリカ、南アメリカなどの「辺境」に派遣された外交官や行政官は、異質な言語や文化、宗教的伝統を理解し、現地の慣習に配慮しつつ外交活動や植民地行政を遂行する必要に迫られた。その結果、ヨーロッパ中心の古典的な外交理念は見直しを余儀なくされ、第一次世界大戦をへて「新外交」の時代に入ると、各国政府は競って組織的な対外文化宣伝活動を展開し、戦後の文化外交へと続く道が開かれた。
この小シンポジウムでは、文化戦略をめぐる近代外交のこうした大転換において、「辺境」の非キリスト教圏に派遣されたヨーロッパ人の「異文化体験」が果たした役割に注目し、イギリス、フランス、オーストリア=ハンガリー、ドイツの4カ国について国際比較を試みる。予定している研究報告はそれぞれ、これら4カ国の外交官ないし植民地行政官が、あるいは個人的関心から、またあるいは本国政府の指示のもとに展開した、文化交流活動および対植民地政策を分析する。
報告1 松本佐保「イギリスの外交力と博物館・美術館」
大英博物館所蔵品のエルギン・マーブルやロゼッタ・ストーンが英国の外交・軍事力により収集されたことはよく知られているが、これら文化遺産が具体的にどのような交渉と、どのような輸送手段で大英博物館に辿り着いたか、それが外交政策とどう関係したかを明らかにした研究は多くない。本報告では大英博物館所蔵メソポタミアの文化遺産に焦点をあて、有翼人面牡牛像などの遺跡を発掘してコレクションを確立した外交官ヘンリー・オースティン・レイヤードの活動を中心に見ていく。レイヤードはまたナショナル・ギャラリーのルネサンス絵画収集にも尽力している。19世紀英国で政治・外交分野で活躍する人物と博物館・美術館関係者には人的な繋がりと重複があり、博物館・美術館のコレクション確立と外交政策がどの様に連動していたかを明らかにする。大英博物館の古代遺跡部文書館所蔵の手書き文書や、ナショナル・ギャラリー文書館所蔵の議事録などを第一次史料として使用する。
報告2 野村啓介「幕末フランス外交代表の異文化経験」
アヘン戦争を主な契機として極東進出を強化したフランスは、アジア地域にさらなる軍事的・商業的拠点を獲得するなか、わが国とも1858年10月に修好通商条約(安政の五箇国条約)を締結して外交関係を樹立した。これによりフランス帝国政府は、わが国に常駐の外交代表を派遣することとなり、デュシェーヌ・ド・ベルクールとロッシュとがあいついで赴任した。
本国政府、とりわけ現地赴任の外交官にとって、わが国との外交関係は未知の異文化との遭遇をも意味したはずである。それでは、このときフランスはいかなる外交体制のもとに日本との関係を構築・維持しようとし、またその駐日外交代表は日本をどのように観察し、いかに任務を遂行しえたのだろうか。本報告では,フランス外務省史料に依拠しつつ、異文化と対峙する外交代表機能に注目することにより、フランスの対日外交にみる異文化経験の具体相に迫り、極東における帝政外交の諸問題を考えてみたい。
報告3 桑名映子「オーストリア=ハンガリー代理公使の見た明治日本」
本報告は、1892年春から4年間、日本に駐在したオーストリア=ハンガリー代理公使ハインリヒ・クーデンホーフを例として、日本をはじめアジア諸国に対する「異文化理解」の一つの可能性を提示する。このハインリヒと日本女性青山みつの間に生まれた次男栄次郎が、のちにパン・ヨーロッパ運動の指導者となるリヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーである。そのためこれまでの研究では、ハインリヒは主として「光子」の夫、リヒャルトの父として言及され、外交官としての活動や業績に光が当てられることは少なかった。この報告では、ウィーンの帝室・宮廷・国家文書館に所蔵されている本国外務省宛報告書類、チェコ共和国プルゼニュ地方文書館所蔵の「クーデンホーフ家文書」に含まれる家族宛書簡・文書類を手がかりに、日本および非西洋世界に対するこの人物の視角を、日清戦争期の外交指導者、陸奥宗光や伊藤博文との交流とあわせて検討する。
報告4 中村綾乃「ヴィルヘルム・ゾルフとドイツ領サモア統治」
ヴィルヘルム・ゾルフは、ドイツ領サモアの総督、植民地長官、外務大臣を歴任し、第一次世界大戦後に駐日大使として来京した。知日家であり親日家、1920年代の文化外交の立役者として知られている。晩年のゾルフは、ヒトラー政権と対峙し、ナチズムの対抗軸を形成したが、1936年に病死した。サモア総督としての経験は、彼の植民地統治理論を形作り、日本の植民地政策にも影響を与えた。
19世紀中葉、欧米列強の進出とともに、サモアでは「混血児」や「ハーフカースト」と呼ばれる人々の人口が増加した。ドイツ統治下では、労働需要の高まりとともに、多くの中国人が年季労働者としてサモアへ移入した。本報告では、ドイツ領サモアにおいて、ゾルフが主導した「混血児」と中国人労働者の法的身分をめぐる政策を検討する。さらに、この「混血児」と中国人労働者の位置づけが同じドイツ人同士の社会層、宗派や党派の対立に投影されていく過程に注目していく。